春先の雨が降る夜、24歳の理沙(りさ)は家で一人、知らない番号からの着信を受けた。「もしもし?」と出ても、相手は何も言わない。ただ、無音の中にかすかな子供の声が混じる。「見つけて…私を…」そんな言葉が響くように耳に届く。
理沙は驚きながらも、深呼吸をして電話を切った。気味が悪いが、いたずら電話だと自分に言い聞かせる。しかし、その夜、彼女は不思議な夢を見た。夢の中で、彼女は古びた家の中にいた。埃っぽい空気、薄暗い照明。そこに子供の声が響いていた。
「ここにいるよ…」
目が覚めた時、理沙の手にはなぜか小さな金の鍵が握られていた。どこから来たのかわからない。混乱しながらも、気になる気持ちを抑えきれず、翌日彼女はネットで夢で見た家を探し始める。すると、不気味なことに、夢とそっくりの家が実在しており、しかも彼女の住む街にあることがわかった。
行かずにはいられない衝動にかられた彼女は、その家に向かった。そこはもう誰も住んでいない廃屋だった。手元の鍵を試すと、鍵穴にぴったりはまった。そして扉を開けると、一気に冷たい空気が彼女を包み込んだ。
中に入ると、彼女の頭の中に知らない記憶が溢れ出す。子供の笑い声、家族の食卓、そしてある夜の悲鳴。それは明らかに彼女の人生にはなかったもの。それなのに、あまりにもリアルで、彼女はその記憶が「誰か」のものであることを確信する。
そして、奥の部屋へ足を踏み入れた瞬間、彼女は床に小さな手形がいくつも残っているのを見つけた。その手形の中心には、一言。
「ありがとう。これで解放される。」
その瞬間、理沙の心に強烈な安堵感と同時に、ある種の喪失感が襲った。それは、彼女自身が誰かの記憶に触れてしまった代償だったのかもしれない…。



































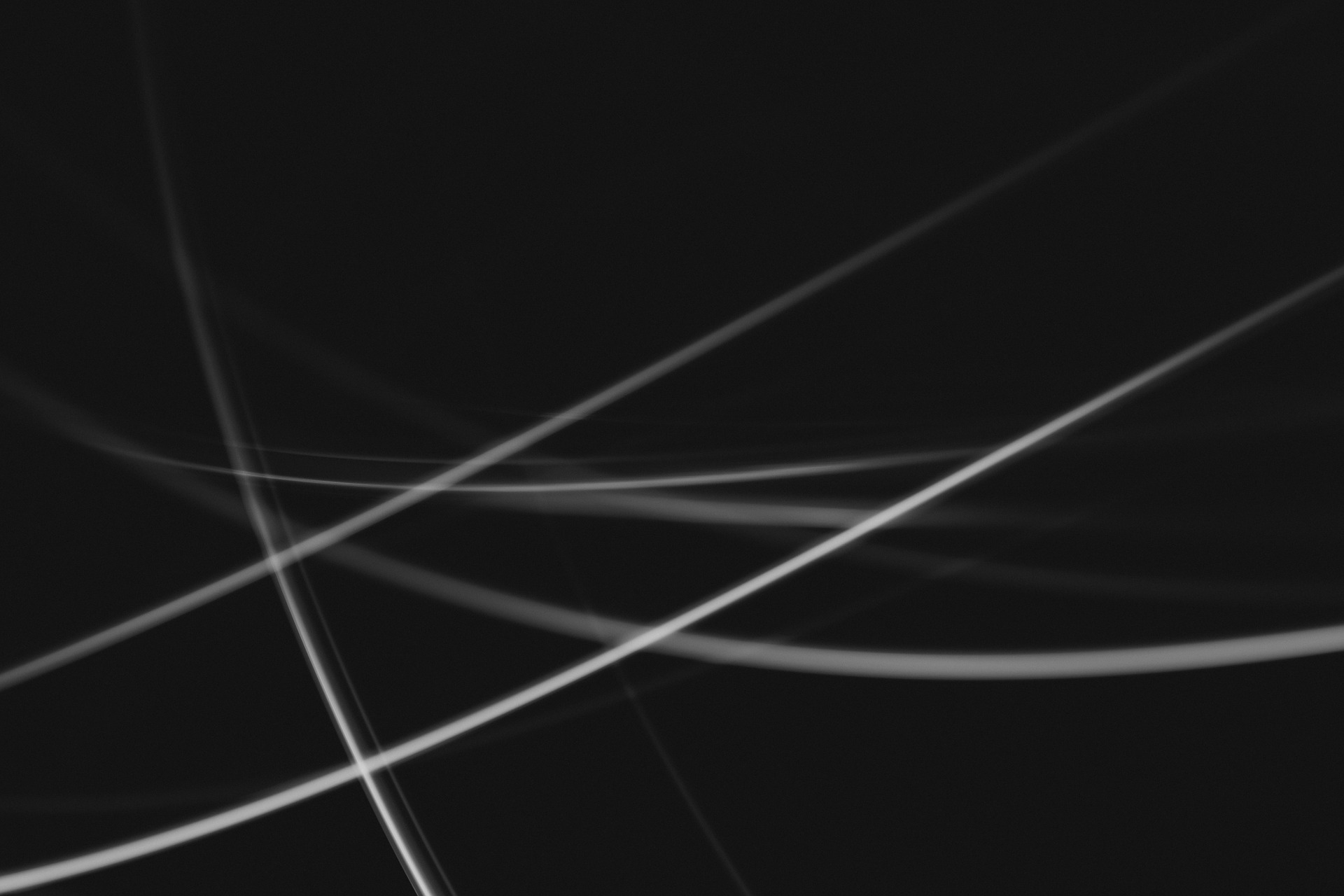




※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。